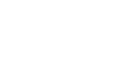令和7年度宮崎県剣道段位審査について
宮崎県剣道連盟
1 実技、日本剣道形、学科について行う。
2 審査科目の内容は、次の通りとする。
(1)実技審査 ※1・・・「剣道指導要領」全剣連発行を参考にご指導願います
| 受審段位 | 実技の内容(※1) | 実技審査上の着眼点 |
| 初 段 | 切り返・面・小手・小手面 ・立会(30秒程度) |
「基礎的技能」・・・竹刀操作と踏み込み動作が協応し、適正な姿勢で発揮出来たか否か |
| 二 段 | 切り返し・立会(60秒程度) | 「基本的対人技能」・・・上記に加えて仕掛け技の適時性や気勢・体勢・刀勢の適正・充実が見られるか否か |
| 三 段 | 立会(90秒程度) | |
| 四・五段 | 立会(90秒程度) | 「対人的応用技能」・・・溜め→崩し(誘い出し)→捨て身の打ちが円滑に発揮され、仕掛ける技と応じて打つ技が適時に発揮されたか否 |
(2)形審査 (※実技審査合格者のみ受審可)
| 受審段位 | 日本剣道形の審査本数 |
| 初 段 | 太刀の形三本(一本目・二本目・三本目) |
| 二 段 | 太刀の形五本(一本目・二本目・三本目・四本目・五本目) |
| 三 段 | 太刀の形七本 |
| 四・五段 | 太刀の形七本と小太刀の形3本 |
| 日本剣道形の審査上の着眼点(初段から五段まで共通) | |
| 1 | 立会前後の作法、立会の所作、木刀の取り扱いを適切におこなっているか |
| 2 | 五つの構え、小太刀の形における半身の構え、入身の所作を正しく行っているか |
| 3 | 目付け、呼吸法等を心得、終始充実した気勢、気迫を持って合気で行い、段位にふさわしい迫真性、重圧性が見受けられるか |
| 4 | 打太刀、仕太刀の関係を理解し、原則として仕太刀は打太刀に従って始動しているか |
| 5 | 太刀の形においては、「機を見て」小太刀の形においては、「入身になろうとするところを」とある打突の時機は適切か |
| 6 |
各本ごとの理合を熟知し、技に応じた打突の度合い緩急強弱を心得一拍子で行っているか |
| 7 |
打太刀は、一足一刀の間合いから打突部位を打突し、仕太刀は物打で打突部位を確実に打突しているか |
| 8 |
太刀を振りかぶる度合いを心得、振りかぶり過ぎて剣先が両拳の高さより下がってはいないか |
| 9 |
足さばきはすり足で行い、打突した時、後ろ足を残さず前足に伴ってひきつけているか |
| 10 |
仕太刀は打突後、十分な気位で残心を示しているか 打太刀は仕太刀の十分な残心を見届けてから始動しているか |
(3) 学科審査 (※実技、形合格者のみ受審可)
※「剣道学科審査の問題例と解答例」全剣連発行より出題する
| 受審段位 | 筆記試験の内容 |
| 初 段 | ①「中段の構えの姿勢で注意すること」について説明しなさい ②「足さばき」について説明しなさい ③「三つの間合」を書きなさい ④「基本打突や技の練習」で気をつけることを述べなさい ※上記より1問を選択式問題で出題する ※その他、作文(200字程度)1問(剣道を体験して考えたことを問う) |
| 二・三段 | ①剣道で「礼儀を大切にする理由」について述べなさい (知識・理論) ②「正しい鍔ぜり合いと注意点」を説明しなさい (実技 基本) ③「残心」について説明しなさい (実技 述語心理的要因) ④日本剣道形を実施するときの「足さばき」で気をつけることを書きなさい (日本剣道形) ※上記4問から2問を記述式で出題する |
| 四・五段 | ①「下位者と稽古するときの留意点」について述べなさい (知識・理論) ②「残心の重要性」について述べなさい (実技 述語心理的要因) ③全日本剣道連盟「剣道試合・審判規則」第1条に「剣の理法を全うしつつ、公明正大に試合をし、適正公平に審判をする」とあるが、これはどのような意味があるか (解答:剣道試合・審判・運営要領の手引きP3) ④全日本剣道連盟「剣道試合・審判規則」第12条にある有効打突の条件と、有効打突の要素・要件をそれぞれ5つずつ書きなさい (解答:剣道試合・審判・運営要領の手引きP6.7) ※上記4問から2問を記述式で出題する 解答例の丸暗記ではなく、解答例を基に自分の考えを入れた記述をして欲しい。 |
3 その他
形または学科審査の不合格者は、再受審をすることができる。 再受審の受審期間は、不合格となった当該審査の日から1年以内とし、回数は1回限りとする。 (称号・段位審査細則第15条)